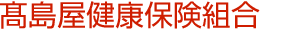家族の保険給付一覧
法定給付(健康保険法で決められた給付)
| 病気やけがを したとき |
家族療養費 | 医療費の7割を健保組合が負担 (未就学児童は8割。70歳以上75歳未満は8割〔ただし、現役並みの所得のある世帯は7割〕となります。) |
|---|---|---|
| ★家族療養費 | 緊急等で立て替え払いした後で健保組合に申請すれば一定基準で現金を支給 | |
| 家族高額療養費(※1) |
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(70歳未満の計算) (高額療養費に関しては、他に世帯合算、多数回、介護合算などの負担軽減があります) |
|
| 家族訪問看護 療養費 |
定められた全費用の7割を健保組合が負担 | |
| 家族入院時 食事療養費 |
1食あたり510円(1日3食を限度)を超えた額を支給 | |
| ★家族移送費 | 申請要件に基づき健保組合が認めた場合には実際にかかった費用を支給 | |
| 高額介護合算療養費 | 同一世帯において1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超過分を医療にかかった自己負担の比率に応じて按分した額を支給 | |
| 出産したとき | ★家族出産育児一時金 | 1子につき500,000円 ただし、在胎週22週未満の出産や産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は488,000円 |
| 死亡したとき | ★家族埋葬料 | 50,000円 |
- ★申請書が必要な給付です。申請手続きは、各事業所にて行ってください(申請書は申請書ダウンロードより印刷できます)。ただし、出産育児一時金および家族出産育児一時金は申請が不要な場合があります。
-
※1 自己負担が高額になりそうな場合
「限度額適用認定証」の事前提示で窓口支払いが自己負担限度額までになります。
医療機関窓口で支払う自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えたときには、その超えた額が(家族)高額療養費として後日還付されますが、事前に「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関窓口では自己負担限度額だけ支払えばよいという制度があります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
| 適用区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
|---|---|---|
| ア | 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% *<140,100円> |
| イ | 標準報酬月額 53~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% *<93,000円> |
| ウ | 標準報酬月額 28~50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円) ×1% *<44,400円> |
| エ | 標準報酬月額 26万円以下 |
*<44,400円> 57,600円
|
| オ | 低所得者※ (住民税非課税世帯) |
*<24,600円> 35,400円 |
- *< >内は多数回該当(同一世帯が直近1年間ですでに3回以上高額療養費を支給されている場合の4回目から)の自己負担額です。
- ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
付加給付(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
| 病気やけがを したとき |
家族療養費 付加金 |
医療費自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額を支給 ただし、100円未満端数を切り捨て |
|---|---|---|
| 合算高額療養費 付加金 |
同一世帯において同一月に2人以上がそれぞれ21,000円以上の医療費を自己負担した場合、医療費自己負担限度額から1件ごとに25,000円を控除した額を支給 ただし、100円未満端数を切り捨て |
|
| 家族訪問看護 療養費付加金 |
1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円を控除した額を支給 ただし、100円未満端数を切り捨て |